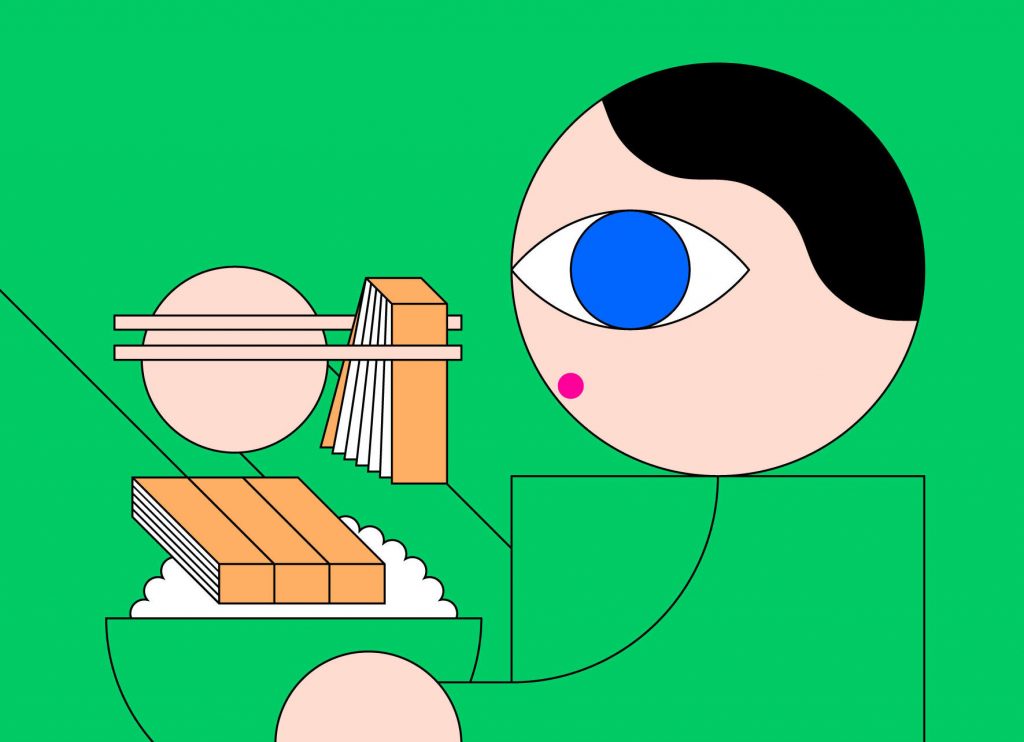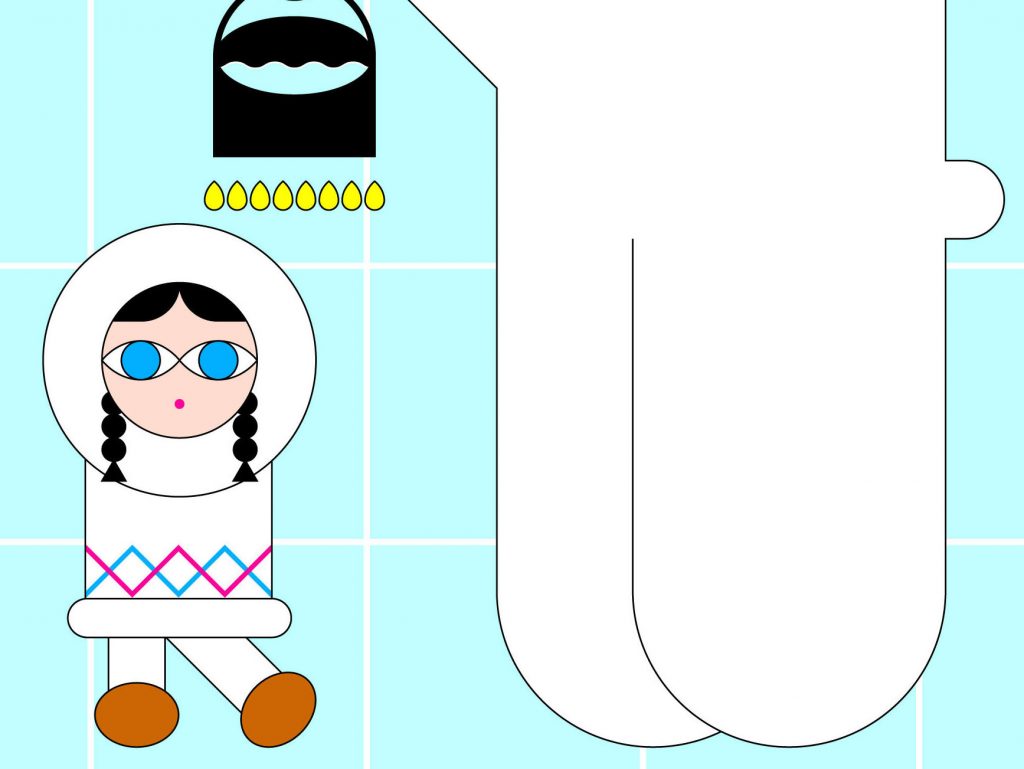ページをめくり、お腹を満たす
ブックディレクター 山口博之さんが、さまざまなジャンルより選んだ、「食」に関する本を紹介する人気連載。気鋭のイラストレーター瓜生太郎さんのコミカルなイラストとともに、“おいしい読書”を楽しんで。
レシピ本を批評するということの意味
Vol.13『食べたくなる本』(みすず書房)著:三浦哲哉
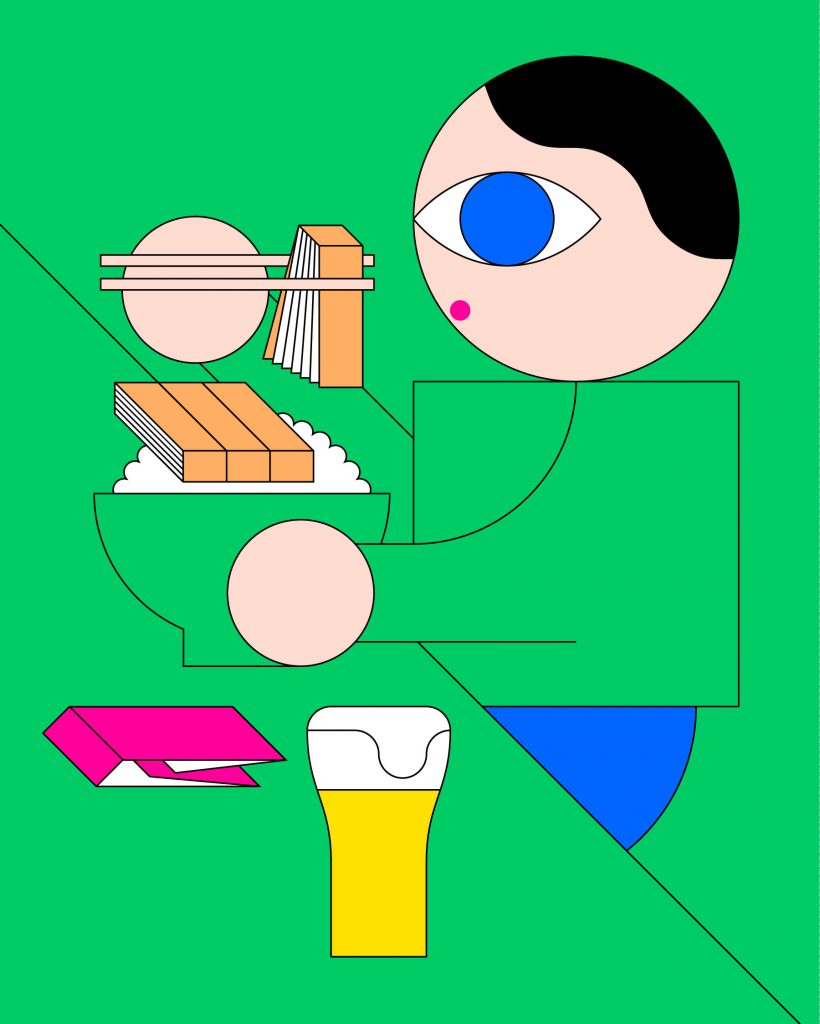
基本的にどんな本であろうとレビューや批評の対象になるはずだが、ある種の本は取り上げにくいことがある。教則本が特にそうだが、書かれていることを実践してみて初めてわかることが多いと言う意味でレシピ本もそのひとつだ。過去たくさんの書評本や批評本が出てきたけれど、レシピ本のそれは出てこなかった。単純に料理してみるのが面倒くさいのか。食べたら眠くなるからか。
映画批評、研究を専門とする三浦哲哉は、実際に料理をしながらこの料理本批評を書いている。取り上げたすべての本のレシピを料理したと書いているわけではないが、きっと試している。そう思わせる説得力と、新鮮な読み応えのある本だ。三浦は、料理家や料理研究家たちのレシピやエッセイなどから、彼/彼女らの哲学や隠されたテーマを読み解き、料理本を読むとはどういうことか、そしてそのレシピで料理を作るとはどういうことかを常にどこかに忍ばせる。
料理の書物には、自分とはべつの基準がまざまざと示されており、レシピ集ならばそれを実際に作って味わうことができる。食についての本を読み、そこで書かれた料理を作るという営みのおもしろさは、自分にとっての「おいしさ」が絶対的なものではないということ、変わりうるということを知ることにこそある。
伝統的な料理について書かれた本であっても、その本は、本であるかぎりで、もはやその料理が生まれた環境——裕福であったり豊かな自然に囲まれていたり家族の絆も支えられていたり——から、切り離されている。それが言葉の力だろう。だからあらゆる料理の本は、自立して、まったくべつの文脈で役立てられるべく、私たちに差し出されている。
丸元淑生から有元葉子、辰巳芳子、高山なおみ、細川亜衣、ケンタロウ、小泉武夫、冷水希三子、奥田政行、勝見洋一まで。本書で取り上げられる料理家たちは、三浦が“べつの基準”と言うような、時に極端なほどに自分の哲学や方法論で食、料理に向き合っている。“自分にできることは、絶対的な基準を持たないということ、というより、複数の基準にたえずさらされ、揺らぎつづけているということ自体を、積極的な価値として捉えてみることだけ”と書く三浦の態度は、そうした料理家たちの極端な愛を一度受け止め、料理を通して確認していくことにも現れている。
濃・淡・濃・淡のビート
ケンタロウのどんぶりを取り上げる回では、塩気が次のごはんを呼び込む“ごはんがすすむ味”について書き始め、“ビールがすすむ味”と重ねていく。ビールを飲むことを予め含んだしょっぱく濃い味。“濃い、淡い、濃い、淡いのビートが私たちを呼ぶのだ”とし、今度はそれをどんぶりという食べ物の垂直的な配置構造及び味わいと重ねていく。深めの容器に盛られるご飯に汁気を含んだ料理が載る。上の具材の濃さと中和するご飯という“濃・淡・濃・淡のビート”がどんぶりには凝縮されていると三浦は言う。食べ方と味わいと物理的な構造という食の大事な要素を見事にスライドさせていきながらつなげている。
取り上げられた中に、実際にお店を持つ料理人、「アル・ケッチァーノ」の奥田政行がいる。奥田が自作の解説に多用する「のような」という言葉を、三浦は「代用の法則」と呼ぶ。それは何かの代わりを何かで代用したからといって、ものの元の味に戻そうというのではない。代用することによって「生ハム」なら「生ハム」というひとつの味が、たったひとつの食味ではなく、“複雑な味と香りの要素から「合成された」”ものであることを気づかせてくれるのだ。こうした気付きは、アル・ケッチァーノで実際に奥田の料理を口にしてその味に驚き、歓喜した後で本を読み、彼の本を見て、さらには作ってみて得られる本ならではの喜びと言えるだろう。

『食べたくなる本』
(みすず書房)著:三浦哲哉
イラスト:瓜生太郎