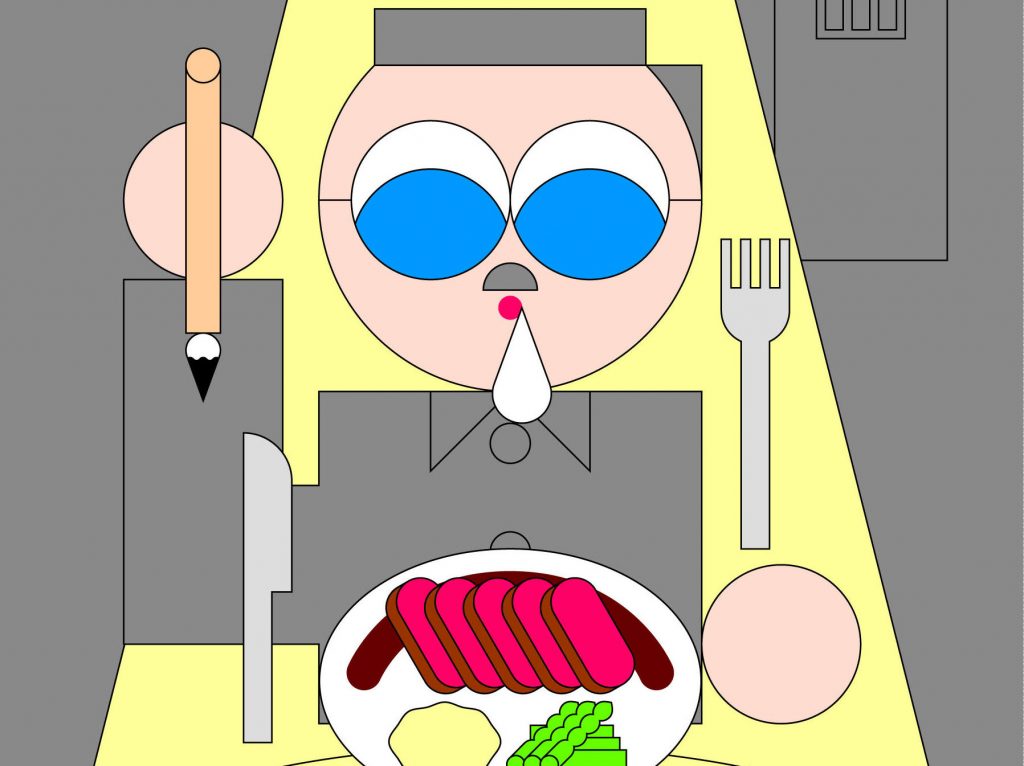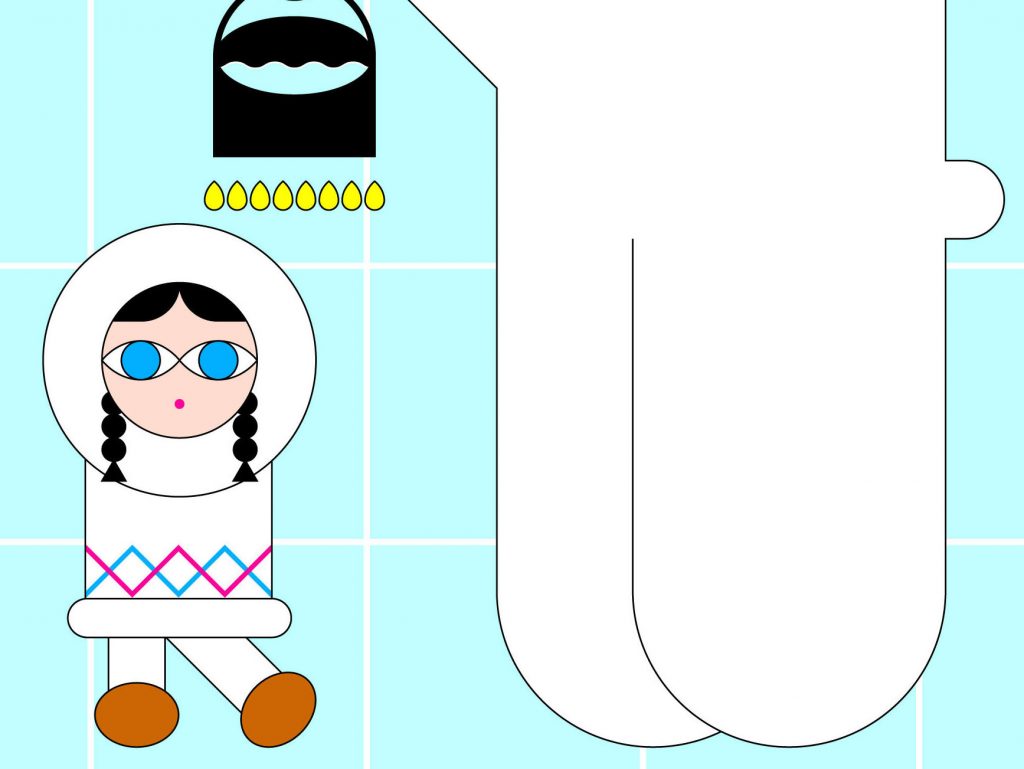ページをめくり、お腹を満たす
ブックディレクター 山口博之さんが、さまざまなジャンルより選んだ、「食」に関する本を紹介する人気連載。気鋭のイラストレーター瓜生太郎さんのコミカルなイラストとともに、“おいしい読書”を楽しんで。
“胃を科学”したら食べられる食材が増える?物理学者が刑務所で考えた、食と味覚の可能性
Vol.8『味覚 清美庵美食随筆集』(中央公論新社)著:大河内正敏
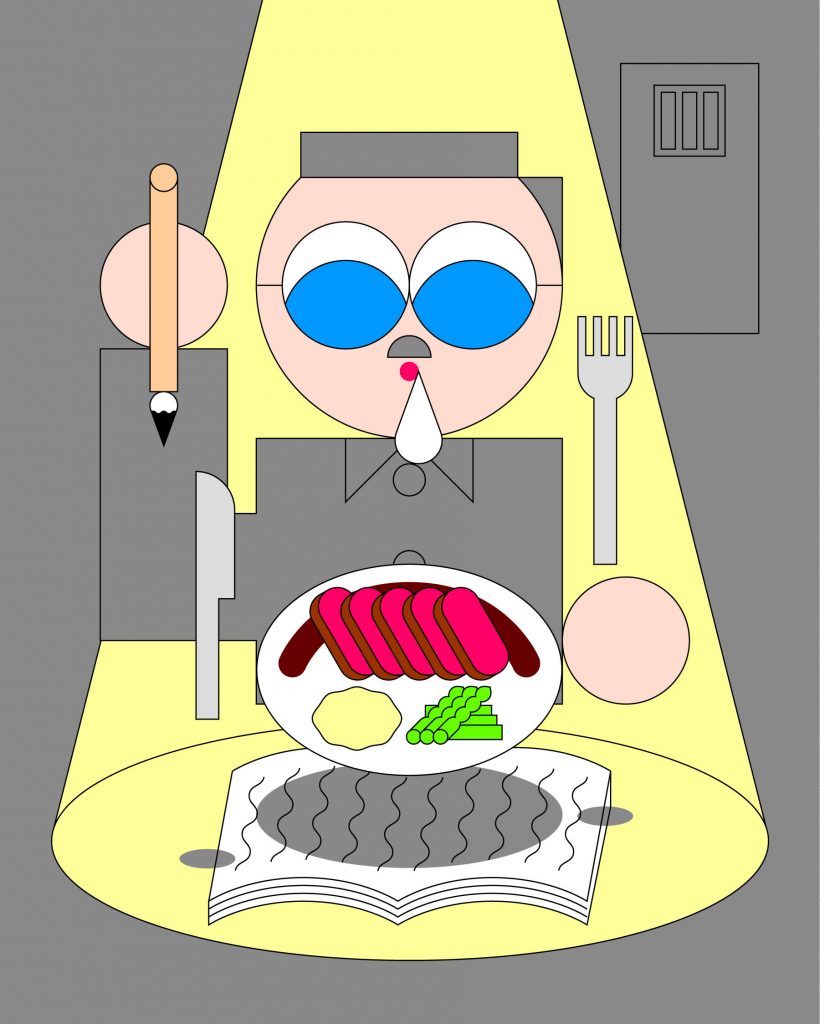
好きなものを食べたい時に食べられないストレスというのがある。お店が遠いのかもしれない。時間がないのかもしれない。お金がないのかもしれない。一緒にごはんを食べる友人と意見が合わないのかもしれない。
この本は、そうした食べたいけれど食べられない環境にいる時に書かれた。著者の大河内正敏(1878〜1952)は拘置所にいた。巣鴨プリズンと呼ばれた太平洋戦争の戦争責任を負った戦犯たちが収容されていた拘置所だ。
物理学者であり貴族でもあった大河内は、1921年から理化学研究所の所長を務め、研究者たちに自由裁量で研究をさせ、その研究結果を事業化。事業会社であった理研コンツェルンによるその売上は、研究費に回され、科学者たちは自由なテーマで好きなだけ研究に没頭した。「科学者の楽園」と呼ばれた理化学研究所を作り出した大河内は、第二次大戦中の原子爆弾研究の責任者として、戦争裁判で裁かれ巣鴨プリズンに収監されていた。
しかし、収監されたのは1945年12月から翌年の4月までの4カ月ほど。『味覚』はその期間に書かれ、翌47年には出版されている。
日本は戦争中から食に飢えてきた。敗戦国となった戦後に十分な栄養とカロリーを得ることは難しい。研究者として理化学研究所所長としてビタミンA剤の発売や合成酒の発明など、食に関わる分野でも多くの応用発明を実現してきた大河内は、国民が飢える、栄養が足りない、という状況に自ら解決案を提案すべき立場と認識していた。
文化と生活の向上。まずはそこだ。食べ物がないのに、主食であった米ばかりを期待し、頼り続けていてはいけない、もっとたくさんの種類の副食物を食べるのだと何度も訴える。「文化の古い国ほど料理は旨いというが、文化が進めば民衆の生活も向上する」。そして「生活を向上するためには、(米を節約して)食道楽や、意地きたなしを、歓迎しなければいけない」と言う。食道楽は食の文化に通じたグルメのことであり、そのグルメとは味覚の発達した人のこと。味覚の発達が調理技術の発達につながり、これまで見向きもしなかった食材たちに光を当てることができ、それらによって食糧事情は大幅に改善できるというのだ。意地汚いことを肯定したのも、食べられるものは何でも食べるということから食の可能性は拡張されると考えていたからだろう。蛙や虫を食材として普及させることを考えていたし、「野鳥の味」や「魚の養殖」「臓物料理」といった章からも、新しい食糧の確保を考えていたことがわかるし、戦前の外食でどんな食材が用いられていたのかがわかるという意味での資料性もある。
大河内は「ガストロノミーの研究も、科学の研究のやり方と、別に違いはない」と考えた。つまりいち早く料理は科学だと考えていた。明治、大正、昭和を爵位のある富裕層として生きてきた男性であり、具体的な調理法などの展開を見せていないのが残念ではある。
蟻が食材になるほど食材の可能性が拡張され、分子ガストロノミーがその名を得るほどに普及してきた現代に大河内が生きていたら、大喜びでエル・ブリやノーマに通い興奮しただろう。うまいものが食べられない境遇で書かれたこの本の食欲は、“胃の科学”であるガストロノミー的にも正当だ。

『味覚 清美庵美食随筆集』
(中央公論新社)著:大河内正敏
イラスト:瓜生太郎